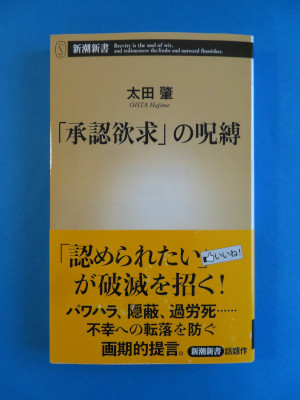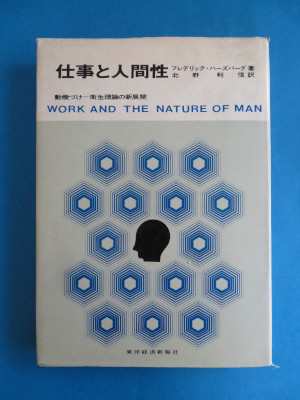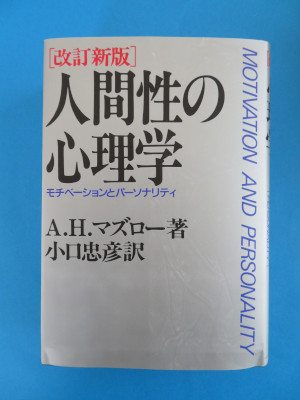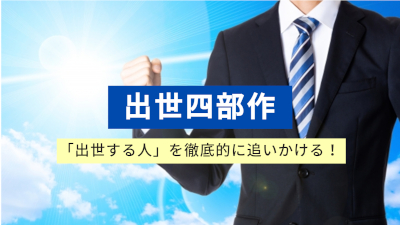2025.03.14更新
上司は承認欲求を部下にも求めています。上司の承認欲求を充たす行動をとれば、上司との関係がよくなることは間違いありません。
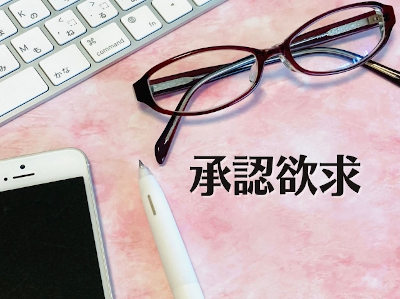
承認欲求が強い上司への対策を考えていきましょう。
残念ながら、今まで上司の承認欲求は見落とされてきました。
私の知る限り、このことに触れている本が一冊あります。
太田肇氏は『「承認欲求」の呪縛 (新潮新書)』のなかで、
『承認欲求の呪縛」は地位の低い側に生じるとはかぎらない。逆に上位者が下位者に依存して生じる場合もあるということを見逃してはいけない。
と述べています。
なぜ上位者の承認欲求が見落とされてきたのでしょう?
それにはハーズバーグの「動機づけ要因ー衛生要因」の研究が深く影響していたとのではないかと考えます。
ハーズバーグは「承認」を動機づけ要因の一つに挙げました。
著書『仕事と人間性―動機づけー衛生理論の新展開』を読むと、「動機づけー衛生理論」はおびただしい数の実証研究に裏づけられていることがわかります。
それは上位者が下位者に与える承認の効果だったのです。
承認欲求といえば下位者が上位者に求めているものと思うようになったのは、この理論が現実に符合していたからです。
現に半世紀を経た現在でもこの理論は受け継がれています。
『仕事と人間性』
しかし、承認欲求自体はほとんどの人が持っている欲求です。
このことは承認欲求の大元になったマズローの著書を読むとわかります。
マズローは承認欲求は2つに分けられると述べています。
一つは、強さ、達成、適切さ、熟達と能力、世の中を前にしての自信、独立と自由などに対する願望
もう一つは、(他者から受ける尊敬とか承認を意味する)評判とか信望、地位、名声と栄光、優越、承認、注意、重視、威信、評価などに対する願望です。
(『人間性の心理学―モチベーションとパーソナリティ』第四章から)
マズローは承認欲求を下位者が上位者に求めるような欲求などとは考えておらず、人間の基本的欲求の一つとしてとらえているのです。
(注 マズローは説明のなかで、「承認の欲求」を「自尊心の欲求」とも表現している)
上司も人であり、承認の欲求すなわち人から尊敬され、認められたいという欲求を持っているのです。
『人間性の心理学』
問題は、私たちは、この上司の承認欲求にどのように対応をしてきたかということです。
きっとビジネスマナー的な対応をしてきたのではないでしょうか。
上司への挨拶、報連相、上司からの指示の受け方、席次などを上司へのマナーと考え、マナーを適切に行うことで上司の存在を認めてきたのです。
このことはビジネスマナーの本を見れば明らかです。
上司へのビジネスマナーが適切に行われると、上司は満足を覚えることは間違いありません。
その意味で、ビジネスマナーは上司の承認欲求を充たす一定の役割を果たしていたことになります。
しかし、上司は本当にそのような承認に満足しているのでしょうか?
適切なビジネスマナーは形としての承認です。
上司はもっと内面的な承認を求めているのではないでしょうか。
上司への内面的な承認の具体例はどのようなものでしょう?
その代表格は上司への「アドバイスをお願いします」だと思います。
『「出世しぐさ」のすすめ』のなかで、「『アドバイスをお願いします」と言われると、なぜ嬉しくなるのか」について書きましが、
この言葉は上司からすれば自分の経験や能力が認められたことを意味します。
つまり内面的な承認なのです。
その他にもいろいろありそうです。
ビジネスの世界では上司に自分の得意先に行ってもらうことは多くあります。
その際、お礼を言うのはビジネスマナーとして当然ですが、上司は、その結果、自分が役に立ったどうかを知りたいのです。
たとえば「部長に訪問いただいたおかげで、事態が進展しました」という部下からの報告があれば、上司は自分の経験と能力が役に立ったと思えるでしょう。
この部下からの報告は、まさに自分への承認なのです。
また、会議の席上、上司から意見、提案が出されることがあります。
その内容は、部下が考えてもいなかったことが多くあります。
そんなとき、もし誰かが「そんな視点で考えたことはありませんでした」と率直に意見を言ったなら、上司は自分の経験と能力が参考になったと思います。
この部下の発言とその場の雰囲気は自分への承認を示しているのです。
私は、究極的には、上司は部下との共通体験を求めていると考えます。
このことを『エリート社員に打ち勝つ! あなただけの出世術』に書きました。
この共通体験こそが、上司への承認なのです。

しかし、私たちはそんな上司へ承認とはほど遠いことをしています。
上司の得意先への訪問については、お礼を言えれば上出来であり、その後の状況について報告する部下はほとんどいません。
会議の席でも、上司から意見や提案が出されると不快な表情を浮かべ、そんな意見や案は実現不可能とばかりに反論します。
そればかりでない。
会議前の上司への事前説明、資料が不十分なことを棚に上げ、会議の席で上司が少しでも理解不足を示そうものなら、鋭くその点を突き、まるで鬼の首をとったかのような表情を浮かべます。
(前掲『「出世しぐさ」のすすめ』「なぜ、頭がよくても出世できないのか?」より)
上司と一緒に出張に行ったときでも、場当たり的に選んだホテルに上司を泊まらせ、
(前掲『「出世しぐさ」のすすめ』「出張の印象はホテルの部屋で決まる」より)
上司と一緒に得意先を訪問したときも、昼食の候補先など考えもしません。
(『なぜ「できる社員」はビジネスマナーを守らないのか』「『できる社員』は昼食の候補先を用意する」より)
私たちは、仕事を進めていくうえで、また出世や昇進するうえで、上司との関係がいかに重要か知っています。
しかし、上司にも承認欲求があることを見落としています。
ほとんどの人が見落としている上司の承認欲求に気がつくと、人とはまったく異なった上司との関係を築き、出世、昇進への道を歩むことができます。
綾小路 亜也

関連記事:上司が喜ぶ言葉は?
出世は「構え方」で決まります
◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作
こっそり読まれ続けています
ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!
スマホで読む方法
出世するビジネスマナー
「出世しぐさ」のすすめ
※「出世しぐさ」は商標登録されました。
エリートの弱点を突く!
エリート社員に打ち勝つ! あなただけの出世術
新しい出世術
コロナ後の「たった一つの出世の掟」
◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ
印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方
◆メルマガ「出世塾」の情報
(まずは発刊内容をご欄ください)
https://shinyuri-souken.com/?p=28756
◆キャリア理論の本紹介
https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933