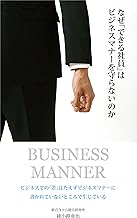|
なぜ「できる社員」はビジネスマナーを守らないのか 綾小路 亜也 2015-09-28 Amazonで詳しく見る |
「できる社員」のビジネスマナーを紹介しています。
「できる社員」はビジネスマナーを鵜呑みにはしません。
自分で考え、自分で作り上げるものだと考えています。
大手金融機関の支店長などを経験してきた著者が、「できる社員」の正体を明らかにしていきます。
[目的、難易度別]ビジネスマナーが効率的に学べるおすすめ本9選で
マナーの本質を踏まえた一冊と紹介されています。
目次
はじめに
「できる社員」はビジネスマナーを自分の頭で考えている
第1章 「差をつける」得意先対応編
「できる社員」は相手の感情を優先する
①折り返しの電話をもらわない
②アポは9時半か13時半
③訪問人数にこだわる
④手土産を席の横に置く
⑤テーブルの上に資料を置かない
⑥資料を会社の封筒から取り出す
⑦メモを極力取らない
⑧相づちをほどほどに打つ
⑨商談を30分以内に収める
⑩辞去するときに神経をつかう
⑪餞別を封筒に入れて渡す
第2章 「差をつける」接待編
「できる社員」は相手に見えない部分で気をつかう
⑫ほどほどにお酌をする
⑬上司にときどきお酌をする
⑭前任者の話題を避ける
⑮受けより自分を知ってもらう
⑯時刻通りに接待を終わらせる
⑰一次会で終わらせる
⑱接待の手土産を自分で選ぶ
⑲手土産をケチらない
⑳「季節のご挨拶」を知っている
第3章 「差をつける」上司への対応編
「できる社員」は上司の本音を知っている
㉑結論から話すのではなく件名から話す
㉒口頭で報告してから文書を作成する
㉓上司の話に割り込まない
㉔上司が好む席を知っている
㉕社用車では迷わず道路側の席に座る
㉖出張先で上司と一緒に朝食をとらない
㉗昼食の候補先を用意する
㉘飲みに誘われたら仕事を切り上げる
㉙居酒屋でオーダーに迷わない
㉚上司と飲んだ翌朝にお礼を言う
第4章 「差をつける」ビジネスマナー実践編
自分の頭で考え、ビジネスマナーで差をつける
㉛ 上司と一緒にタクシーを拾う場合、座る席はどこか?
㉜ 役員が訪ねてきた場合、役員が応接室で座る席はどこか?
㉝ 得意先が数名で来社するとき、確認すべきはなにか?
㉞ 得意先の部長に「ご無沙汰しています」と言うべきか?
㉟ ゴルフ接待で相手のスコアが悪かったとき、どうすべきか?
㊱ お詫び訪問にいくとき、一番重要なことはなにか?
㊲ 少しだけお金を使わなければならない持ち物はなにか?
㊳ ビジネスマンが一番疲れを感じさせるものはなにか?
㊴ 希望通りにいかなかった人の送別会でなんと声をかけるか?
㊵ 「できる社員」とはどういう社員なのか?
おわりに
ビジネスマンの「差」は解釈の違いから生じている
はじめに
「できる社員」はビジネスマナーを自分の頭で考えている
第1章 「差をつける」得意先対応編
「できる社員」は相手の感情を優先する
①折り返しの電話をもらわない
②アポは9時半か13時半
③訪問人数にこだわる
④手土産を席の横に置く
⑤テーブルの上に資料を置かない
⑥資料を会社の封筒から取り出す
⑦メモを極力取らない
⑧相づちをほどほどに打つ
⑨商談を30分以内に収める
⑩辞去するときに神経をつかう
⑪餞別を封筒に入れて渡す
第2章 「差をつける」接待編
「できる社員」は相手に見えない部分で気をつかう
⑫ほどほどにお酌をする
⑬上司にときどきお酌をする
⑭前任者の話題を避ける
⑮受けより自分を知ってもらう
⑯時刻通りに接待を終わらせる
⑰一次会で終わらせる
⑱接待の手土産を自分で選ぶ
⑲手土産をケチらない
⑳「季節のご挨拶」を知っている
第3章 「差をつける」上司への対応編
「できる社員」は上司の本音を知っている
㉑結論から話すのではなく件名から話す
㉒口頭で報告してから文書を作成する
㉓上司の話に割り込まない
㉔上司が好む席を知っている
㉕社用車では迷わず道路側の席に座る
㉖出張先で上司と一緒に朝食をとらない
㉗昼食の候補先を用意する
㉘飲みに誘われたら仕事を切り上げる
㉙居酒屋でオーダーに迷わない
㉚上司と飲んだ翌朝にお礼を言う
第4章 「差をつける」ビジネスマナー実践編
自分の頭で考え、ビジネスマナーで差をつける
㉛ 上司と一緒にタクシーを拾う場合、座る席はどこか?
㉜ 役員が訪ねてきた場合、役員が応接室で座る席はどこか?
㉝ 得意先が数名で来社するとき、確認すべきはなにか?
㉞ 得意先の部長に「ご無沙汰しています」と言うべきか?
㉟ ゴルフ接待で相手のスコアが悪かったとき、どうすべきか?
㊱ お詫び訪問にいくとき、一番重要なことはなにか?
㊲ 少しだけお金を使わなければならない持ち物はなにか?
㊳ ビジネスマンが一番疲れを感じさせるものはなにか?
㊴ 希望通りにいかなかった人の送別会でなんと声をかけるか?
㊵ 「できる社員」とはどういう社員なのか?
おわりに
ビジネスマンの「差」は解釈の違いから生じている
著者紹介
綾小路 亜也(あやのこうじ・あや)
慶應義塾大学卒業後、大手金融機関に入社し支店長、理事を経験。
ビジネス経験に裏打ちされた出世やキャリアアップ、ビジネスマナーの研究家として知られている。2014年、ビジネスパーソンのキャリアアップを支援するために新百合ヶ丘総合研究所を設立。キャリアコンサルタント ビジネスマナーインストラクター
『出世はタイミングで決まる!』『「出世しぐさ」のすすめ』『エリート社員に打ち勝つ! あなただけの出世術』『コロナ後のたった一つの「出世の掟」』など著書多数。企業で働く営業女子への指南書、ハンコの選び方・押し方の本、浅草を舞台にしたエッセイも書いている。
できる社員のビジネスマナー
『なぜ「できる社員」はビジネスマナーを守らないのか』