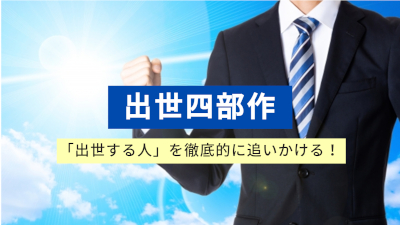2026.01.22更新
職場には妙にアピールする人、出しゃばる人、上司のゴマをする人、自分勝手な人がいますが、心が反応する嫌な人もいます。

自分の意見は正しいとばかりに、言い切ってばかりいる人です。
言い切ってばかりいる人が「嫌な人」だということを、あるビジネス書を読んで改めて知りました。
その本には、なかなかいいことが書かれており、論理もきれいで、内容的にもほとんど正しいと思われました。
しかし、どうも読後感がスッキリしないのです。
それどころか著者の性格のようなものを感じ、本自体すっかり嫌になってしまいました。
「どこが嫌だったんだろう?」と考えてみました。
著者の他の人の考えや行動を受け付けないという言い切りが嫌だったのです。
その「言い切り」は正確に言えば、その時点の知識と経験に基づいた意見です。
だから、(現在の自分の結論では)(自分なりにいろいろ考えた挙句)といったニュアンスを読者が感じるかどうかということが重要です。
この部分を感じられなかったから、本自体が嫌になってしまったのです。

ビジネス社会にも、自分の意見は常に正しく、人の意見は常に正しくないと考える人がいます。
その人にとって会議や打ち合わせは、「正しいか」「正しくないか」を決める場であり、自分が正しくないと思った意見はことごとく斬り捨てます。
職場の人は「どうして、そんなに自信があるのだろう?」と首を傾げます。
こんな人と飲みに行っても全然楽しくありません。
自分の意見は正しいという前提のもとで話をしているからです。
また、「自分を取り囲む人はみんな一流」のようなことも言います。

こんな嫌な人、に職場の人はどう対応しているでしょう?
その人の考えや意見に無関心になる方法で撃退しています。
つまり受け流すということです。
そんなことを知らないのは、当の本人だけです。
今、盛んに「言い切る」ことがすすめられています。
あなたも、きっとセミナーなどで聞いたはずです。
ビジネス書にも、そう書かれているのを目にしたことがあると思います。
その理由はシンプルです。
「~と思う」では、自信なげに思われてしまうからです。
たしかに、判断を求められたとき、「~と思います」では心もとなく映るかもしれません。
だからと言って、何でも「言い切り」は、とても事実に基づいた結論とは言えません。
言い切れるかどうかは、あくまでも事実に基づくのです。
会社社会では、言い切ってばかりいる人は、間違いなく嫌われます。
もちろん、言い切るだけの事実や証拠がある場合は、言い切って構わませんが、言い切ってばかりいる人は、そんなことにお構いなしに、自分の自信を示すために言い切るのです。
ここで、会議や打ち合わせは、何のためにあるのか、考えてください。
知識や経験も考え方も違った人がいるから意味があるのです。
自分が考えもしなかったことに気づくからです。
それゆえ、会議や打ち合わせは、みんなで、それぞれが気づかなかった部分をまとめる上げるためにあるとも言えます。
自分の意見は、あくまでも自分の知識、経験に基づく判断にすぎないということ、自分の知り得ぬことも、考えが及ばないことを知るというが、会議や打ち合わせの趣旨です。
言い切ってばかりいる人がいると、会議や打ち合わせの意味がなくなるからのです。
綾小路 亜也

関連記事:言い切ってよいかは、情報の正確さの問題
◆新百合ヶ丘総合研究所の出世を現実につかむ本
こっそり読まれ続けています
ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!
スマホで読む方法
出世するビジネスマナー
「出世しぐさ」のすすめ
※「出世しぐさ」は商標登録されました。
エリートの弱点を突く!
エリート社員に打ち勝つ! あなただけの出世術
新しい出世術
コロナ後の「たった一つの出世の掟」
◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ
印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方
◆メルマガ「出世塾」の情報
(まずは発刊内容をご覧ください)
https://shinyuri-souken.com/?p=28756
◆キャリア理論の本紹介
https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933
出世は「構え方」で決まります
◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作