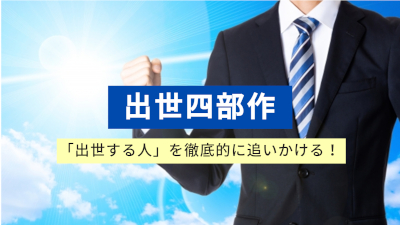2026.01.14更新
席を譲る時、「もしよろしければ、おかけになりませんか?」という言い方をすすめる人がいます。「おかけになりません」は否定形で、「か」は疑問形です。

「否定形+疑問形」になっているのです。
これは「選択権はあなたにあり、私はあなたの希望に沿います」という意思を伝えていると、話し方の専門家である渡辺由佳さんは言います。
何気に使っている「おかけになりませんか?」ですが、こういう構造になっていたのです。
渡辺由佳さんの著書です
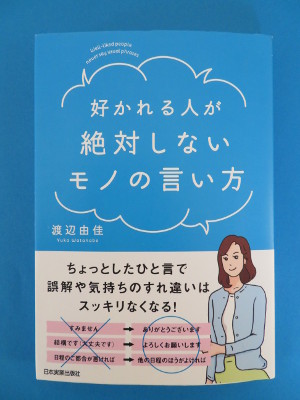
この「否定形+疑問形」はあらゆる場で活用できると思いますが、
部下との間で使ってみたら、どうでしょうか?
上司は部下を気づかい、休憩を促す意味で、「ちょっと休もうか」という声をよくかけます。
しかし、部下はもう少し仕事を続けたいのかもしれません。
だが、上司から「休もうか」と声をかけられたなら従わざるを得ないと思います。
部下は上司からの提案と受けとめるからです。
仕事がうまく進まない部下を見て、「一緒にやろうか」という声もよくかけます。
上司は部下に手を差し伸べたつもりですが、そう言われると部下はことわりにくいのです。
もし「一緒にやらないか」と声をかけたならば、部下は「もう少し自分でやってみます」と言うもしれません。
残業する部下を気づかい、「帰ろうか」という声もよくかけます。
上司は自分と一緒に帰ることにより、部下の仕事にストップをかけたかったからです。
そう声をかけられると、部下は帰り支度をしなければならなくなります。
この場合も「帰らないか」と声をかけたならば、部下は「もう少し頑張ります」と答えるかもしれません。
よく考えてみると、「ちょっと休もうか」「一緒にやろうか」「帰ろうか」は自分が主体となり、相手に投げかけている言葉です。
「自分はこうしたいと思っているけど、どう?」と相手にきいていることになります。
これを「ちょっと休まないか」「一緒にやらないか」「帰らないか」と言えば、
渡辺氏がいうように相手に選択権があり、部下は自分の気持ちを伝えることができます。
日本の会社や組織では、ほとんどの上司が部下を気づかっています。
しかし、部下の声が反映した多面評価や他の人が実施した部下へのヒアリング結果を見ると、上司は驚きます。
自分はいつも部下のことを気づかい、声をかけていたのに、部下は「意見を聞いてもらっていない」「やらされ感がある」などと答えていることが多いのです。
もし「否定形+疑問形」で聞いていたならば、きっと違う展開になっていたのです。
・出世や昇進をめざす人へ
上司の解決案を、「指示された」と受けとめてしまう部下がいることを、
『ビジネスマンが見た 出世はタイミングで決まる!』に書きました。
そのことで、出世のタイミングを逃してしまう人がいるのです。
部下は、上司が考える以上に「やらされ感」を持っているのです。
綾小路 亜也
部下から指示されたと受けとめられないことが大事

関連記事:反対意見の言い方は?
◆企業で働く人のビジネスマナー(発行書籍)
出世するビジネスマナー
「出世しぐさ」のすすめ
スマホで読む方法
※「出世しぐさ」は商標登録されました
情報を軸にした 新しいビジネスマナー
本の目次
※「情報セキュリティ時代のビジネスマナー」は商標登録が認められました。
できる社員のビジネスマナー
本の目次
ビジネスマンのハンコの押し方・持ち方
印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方
本の目次
◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ
ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!
◆メルマガ「出世塾」の情報
(まずは発刊内容をご欄ください)
https://shinyuri-souken.com/?p=28756
◆キャリア理論の本紹介
https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933
出世は「構え方」で決まります
◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作