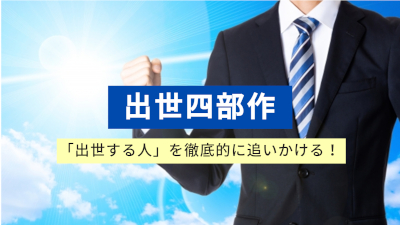2025.10.25更新
今は「出向=左遷」とは言えない時代です。若い時の出向はキャリアアップのチャンスであり、定年を前にした出向は、新しいキャリアへの出発点となります。

重要なことは、若い時も定年を前にした時も、出向を前向きに捉えることです。
1.若い時の出向は、キャリアアップの大きなチャンス
なぜ、若い時に出向を命じられる人がいるのでしょう?
その目的は大きく二つに分かれます。
一つは、専門知識を修得してもらいたいからです。
もう一つは、出向先との関係を、将来にわたって維持したいからです。
いずれも会社に帰って、出向先で得た知識や人脈を活かしてもらうことを前提にしています。
このことを、もう少し掘り下げてみましょう。
日本の企業は、人事、経理、総務、営業、開発といった職能別組織をとっていることが多いです。
ということは、それぞれの組織は専門性をもっていることになります。
しかし、その専門性は会社を回していくための、一般性が高い専門性です。
その職務を専門に行っている会社には及ばないということです。
そして、もっと細分化した専門性も存在します。
たとえば業種別の営業、システム自体の構築、特定の管理業務を対象にした専門性です。
しかし、それらの専門性を得ようとしても、社内には人材がいません。
そこで、これらの専門性を修得させるために、若手社員を出向させるのです。
出向先が、官公庁といった場合もあります。
若手社員なら頭も柔軟で修得も早いですし、出向明けも出向先で得たウハウやスキルを業務運営で活かせるからです。
それらを活かす時間も十分にあります。
これが、出向の第一のパターンです。
出向後は、その分野のスペシャリストに

もう一つのパターンは、人材交流、関係維持を目的にした出向です。
出向先が、出向元の業務と関連性があれば、会社に戻ってきても、培った人脈を基に、有益な情報を入手できます。
出向先が他業種の場合でも、将来、特定分野での業務提携の可能性があるかもしれません。
いずれの場合も、出向先と付き合っていくことに、会社としてメリットを感じているのです。
それゆえ、関係を維持するために、出向させています。
こうしたことから、出向先は親密企業となることが多くあります。
親密企業と相互に出向者を交換していることもあります。
出向の二つのパターンを見て、もうおわかりでしょう。
会社は、専門知識やノウハウ、あるいは人脈を持ち帰ることができる人を、出向に選んでいるということです。
また、出向先で上手く溶け込める人を選んでいます。
そして、出向者には大きなメリットがあります。
社内ではけっして得られない他組織の業務や風土を学んだということです。
社外人脈も持ったということである。
このことは本人のキャリアップに大きくつながります。
若い時の出向は、出世コースと言えるのです。
人脈構築の意味も大きい
2.定年を前にした出向は、第二のキャリアのスタート
一方、定年を前にした出向を「出向=左遷」と捉える人は多いと思います。
グループ会社や取引先などに出向することが多いからです。
しかも一定期間の出向期間を終えると、出向先に転籍することも多くあります。
ということは、自分が慣れ親しんだ会社を去らなければならないということです。
その寂しさ、つらさは痛いほどわかります。
その背景に、会社側の施策を感じ取る人もいるでしょう。
出向先との交渉で、給与を一部負担してもらうことも可能だからです。
そうすれば、人件費の削減につながりますし、出向者が転籍すれば、将来の処遇を心配する必要もなくなります。
実際、そんな思いから、出向先の開拓を精力的に行っている企業もあります。
定年を前にした出向は、そんな会社側の思惑も見えてしまうのです。
慣れ親しんだ会社を離れることはつらいが……

しかし、自分の今後の活躍機会という観点でも、出向を捉えてください。
通常、出向先企業は自分が所属していた会社より、小ぶりなため、活躍できる機会は増えるはずです。
また、出向先企業は、自分が培ってきたことが、現実に活きる場でもあります。
経験してきたことが、直接活きるということもありますし、人との折衝、仕事の進め方などの場面で活きることもあります。
このことは、出向した人は実感としてもっているはずです。
つまり、自分が想像していた以上に活躍できる機会が多いのです。
その結果、出向後、転籍した会社から重宝がられ、定年後、転籍企業で再雇用されたという人も多くいます。
その後も懇願され、その企業で働く人もいます。
また、転籍した会社でのノウハウやスキルを活かし、別の会社で働く人、起業する人までいます。
じつは私も出向ー転籍を経験した一人です。
私の場合、出向先企業の業務と関係する業務を経験したことすらありませんでした。
最初は、企業文化も風土も異なり、システムもまるで異なることから、本当に苦労しました。
しかし、振り返れば、出向し転籍した会社での業務が、長いサラリーマン生活のなかで、一番楽しく、充実感があありました。
それは活躍の場があったからです。
そのため、転籍後の会社で長く働けたのです。
私たちは、入社し育った企業に強い愛着心をもちます。
それは微笑ましいことに違いありませんが、それだけ入社した会社の会社の価値観や人間関係に染まってきたということです。
会社の価値観や人間関係に縛られてきたと言えるかもしれません。
しかし、その価値観や人間関係を永遠に持ち続けることはできません。
いつかは別れを告げなければなりません。
その別れ方の一つが、出向→転籍という形なのです。
最後に、出向後転籍した会社で上手くいった人の共通点についても、述べておきます。
その人たちは、自分が入社し、育った会社の価値観を捨てられたということです。
努力し、出向し転籍した企業の風土に染まったということです。
逆に出向、転籍した会社で上手くいかなかった人は、自分が育った会社の価値観を捨てきれなかった人です。
出向、転籍を自分の新たなキャリアと考えた人は、上手くいったということです。
綾小路 亜也

関連記事:会社社会を生き抜く「専門性」とは?
◆新百合ヶ丘総合研究所のキャリアアップを実現する本のシリーズ
こっそり読まれ続けています
ビジネスマンが見た出世のカラクリ 出世はタイミングで決まる!
スマホで読む方法
出世するビジネスマナー
「出世しぐさ」のすすめ
※「出世しぐさ」は商標登録されました。
エリートの弱点を突く!
エリート社員に打ち勝つ! あなただけの出世術
新しい出世術
コロナ後の「たった一つの出世の掟」
印象アップに踏み切れない人が、ある日突然注目を浴びるハンコの押し方
◆メルマガ「出世塾」の情報
(まずは発刊内容をご欄ください)
https://shinyuri-souken.com/?p=28756
◆キャリア理論の本紹介
https://shinyuri-souken.com/?page_id=41933
出世は「構え方」で決まります
◆新百合ヶ丘総合研究所の出世四部作